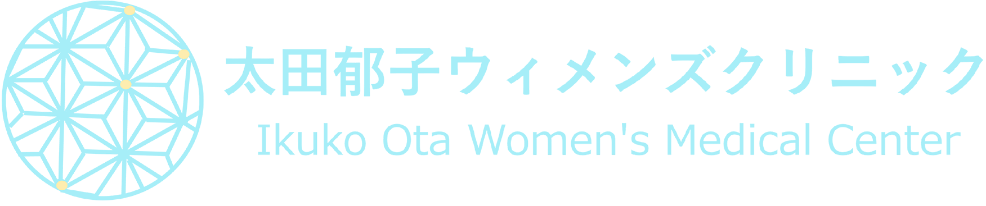不妊治療
不妊症について

不妊症は、生殖年齢に達したカップルが通常の性生活を送り、避妊をしていないのに1年が経過しても妊娠しないという状態です。原因は数え切れないほどありますが、主な原因が女性にあるケースと、男性にあるケースがあります。不妊症が疑われるときに、女性のみが受診されることも多いのですが、実際には男性に原因があるケースも少なくありません。
そのため、不妊症の検査は夫婦ともに受けることが原則となります。
不妊症の検査
不妊症が疑われるときは、必要に応じて内分泌検査、超音波検査、卵管疎通性検査、精液検査などを実施します。内分泌検査は、卵巣の機能に関するホルモンを血液で検査し、ホルモンバランスに異常がないかどうかをチェックします。
卵管が詰まっていると不妊症の原因となるので、卵管疎通性検査はこの状態に陥っていないか確認します。
不妊症の治療
治療としては排卵誘発法の一般不妊治療と、生殖補助医療があります。排卵誘発法はタイミング療法のひとつですが、排卵誘発剤の内服や注射によって卵巣を刺激し、排卵を起こさせます。排卵誘発剤は、卵子を育てる薬と排卵を促進させる薬の二種類に分けられます。排卵誘発法は排卵障害がある場合に限らず、原因不明の不妊などに対しても有効なため、不妊治療には欠かせない治療法と言えます。
生殖補助医療(ART)は精子、卵子、受精卵に体外操作を加えて妊娠を目指す技術で、体外受精や顕微授精などがあります。