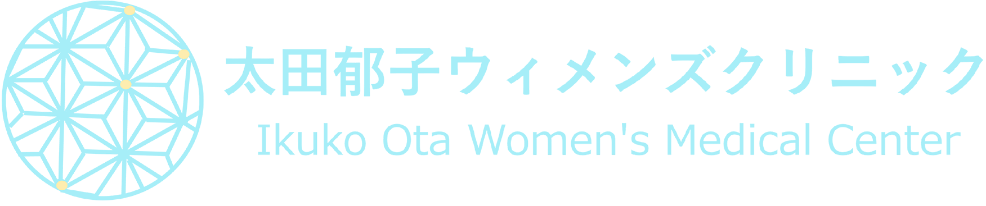ワクチン・検診
子宮頸がんワクチン

子宮頸がんの発生にはヒトパピローマウイルス(HPV)が関わっています。このウイルスは子宮頸がんの患者さまの90%以上で見つかることが知られており、長期にわたって感染すると、がんのリスクが高まります。実際には、HPVに感染しても自然に排出されるケースが多くみられます。しかし、ウイルスが自然に排出されず、数年から数十年にわたって持続的に感染した場合は、がんになることがあるのです。
このようなリスクを減らすには、子宮頸がんワクチンを接種することが大切です。適切な時期にワクチンを接種することにより、HPVの感染を予防できます。使用するワクチンには、2価 HPV ワクチン、4価 HPV ワクチン、9価 HPV ワクチンがあります。2価 HPV ワクチンは、子宮頸がんから多く見つかる HPV 16型と18型の感染を防ぎます。4価 HPV ワクチンは、HPV16型、18型に加えて、尖圭コンジローマの主要な原因となる HPV 6型と11型の感染も防ぎます。9価 HPV ワクチンは HPV16、18、31、33、45、52、58型に加えて、HPV6型と11型の感染も防ぎます。
ワクチン接種後にみられる主な副反応は、発熱、接種した部位の痛みや腫れ、恐怖や興奮をきっかけとした失神などが挙げられます。予防接種を受ける際は、ワクチンの有効性とリスクを十分にご理解いただいた上で、お受けになるかどうかをご判断ください。
子宮頸がん検査
当院では、受診された方の不安などにも配慮し、子宮頸がん検査を行います。内診では専用の診察台に上がり、膣鏡で頸部の状態を見て確認します。子宮頸がんの細胞診検査は、柔らかいブラシを膣に挿入し、子宮頸部の粘膜を軽く擦るようにしながら採取します。まれに少量出血することがありますが、痛みはほとんどありません。必要に応じてHPV検査やコルポスコピー診、組織診を追加します。コルポスコピー診では膣拡大鏡を用いて子宮頸部を観察し、子宮頸部病変の程度と広がりを把握します。組織診では、鉗子を使って組織を採取します。
子宮体がん検査
子宮体がん検査では、子宮の内部に細い棒状の器具を挿入して細胞を採取する、子宮内膜細胞診が一般的です。疑わしいところがある場合や細胞診検査結果が陽性の場合は、組織を採取します。ただ子宮体がんの組織診は、子宮の奥に器具を入れて内膜組織をかき取るため痛みを伴い、組織を採取することが難しいケースもあります。そのような場合はMRI検査を追加することもあります。